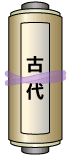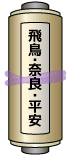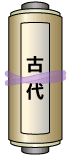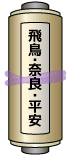|
-
-
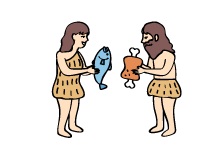
人々は欲しいものがあるときには、自分の持っているものと欲しいものとを取りかえる物々交換をしてくらしていました。
次第に、米・布・塩などが貨幣のような役割をはたすようになり、欲しいものがあるときには、米・布・塩などと交換するようになりました。これらを物品貨幣といいます。
|
 |
- 683年
-
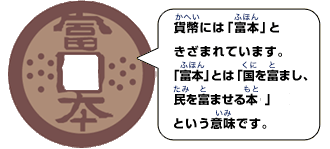
中国の「開元通宝」をモデルとして「富本銭」がつくられました。
|
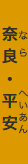 |
- 708年
-

和同開珎
「和同開珎」がつくられました。それから250年の間に、金貨1種類、銀貨1種類、銅銭12種類[皇朝十二銭]がつくられました。
その後、豊臣秀吉が金・銀貨幣をつくるまでの約600年間、日本で貨幣がつくられることはなく、中国から輸入した貨幣がつかわれていました。
|
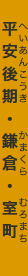 |
-
-

宋銭
宋(中国)との貿易で砂金を輸出し、かわりに宋の銅銭を輸入して日本国内で使っていました。
- 1404年
-
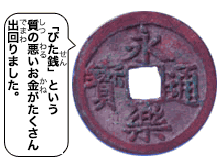
永楽通宝
明(中国)と室町幕府との間に条約が結ばれ、貿易が始まりました。銅銭は、ますます重要な輸入品となり、特に「永楽通宝」は、人気があり、全国でつかわれました。
|
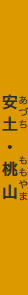 |
-
-

甲州金
16世紀の中頃になると、金銀の採掘がさかんになり、金山や銀山を手に入れた戦国大名は、金貨や銀貨をつくりました。中でも有名なのは、武田信玄がつくった甲州金です。
- 1587年~
-

天正長大判
豊臣秀吉が金貨や銀貨をつくり始め、天正16年(1588)には「天正長大判」や「天正菱大判」などをつくりました。これらは、おもにほうび用として使われ、庶民はあいかわらず明銭やびた銭をつかっていました。
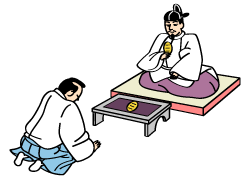
|
 |
-
-
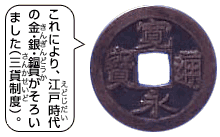
寛永通宝
徳川家康が日本ではじめて貨幣制度を統一し、全国で使うことのできるようにと金・銀貨をつくりました。
- 1636年
-
徳川家光が「銭座」を設置し、銅銭(寛永通宝)をつくり始めました。
- 1695年
-
【元禄の改鋳 】
金貨・銀貨の質を落として貨幣の数量を増やし、幕府の財政難を切りぬけようとしましたが、物価が上がって人々を苦しめる結果となりました。その後、江戸末期まで貨幣の改鋳がくり返されました。
【金貨の海外流出】
ペリーが来航し、日本が開国へとあゆみ始めたころ、日本と海外との金銀交換比率の違いを利用してもうけようとする外国商人たちによって大量の金貨が海外へ流出しました。
- 1866年
-
このように混乱した貨幣制度を整えることを約束した「改税約書」をアメリカ・イギリス・オランダ・フランスと結びましたが、約束をはたせないまま時代は明治へと移っていきます。
|
 |
- 1868年
-
近代的な貨幣制度を整えるため、明治新政府によって造幣局の建設工事が大坂で開始され、1870年に近代的な造幣工場が完成し、1871年に創業式が行われました。
![創業式[写真]](https://www.mint.go.jp/mint/themes/mint/kids/img/history/sougyoushiki.jpg)
創業式[写真]
- 1871年
-
![20円金貨[裏]](https://www.mint.go.jp/mint/themes/mint/kids/img/history/20en_ura.gif)
20円金貨[裏]
![20円金貨[表]](https://www.mint.go.jp/mint/themes/mint/kids/img/history/20en_omote.gif)
20円金貨[表]
新貨条例が制定され、金本位制(金1.5グラム=1円)の下で「円」が誕生しました。その後、金貨・銀貨・銅貨が発行されました。
- 1882年
-
日本の中央銀行として日本銀行が設立されました。
- 1897年
-
貨幣法が公布され、金0.75グラム=1円に変更されました。
|
 |
- 1920年
-
第一次世界大戦時にヨーロッパの国々が金の輸出を停止したことをうけ、日本も金本位制を停止し、金貨幣の製造を休止しました。
|
 |
- 1932年
-
金本位制が完全に停止し、管理通貨制へ移行しました。
- 1938年
-
臨時通貨法が公布され、補助貨幣の製造が始まりました。
- 1964年
-
初めての記念貨幣である「東京オリンピック記念貨幣」が発行されました。

- 1987年
-
「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」が制定され、本日にいたっています。
|